🩺 降圧薬の種類と正しい使い方:血圧を安全にコントロールするために
🌿 はじめに
「血圧の薬を飲み始めたけど、種類が多くてよく分からない」「副作用が心配…」
そんな不安を抱く方は少なくありません。
実は降圧薬(血圧を下げる薬)にはいくつもの種類があり、体質や病気の状態によって使い分けられます。
この記事では、代表的な降圧薬の種類と、それぞれの特徴・注意点をわかりやすく紹介します。
1️⃣ 降圧薬の主な種類と特徴
| 分類 | 主な薬剤例 | 作用のしくみ | 注意点 |
|---|---|---|---|
| ① ACE阻害薬 | エナラプリル(レニベース)、リシノプリルなど | 血管を広げるホルモン(アンジオテンシンⅡ)の働きを抑える | 空咳が出ることがある。腎臓が弱い人は注意。 |
| ② ARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬) | ロサルタン(ニューロタン)、テルミサルタン(ミカルディス)など | 血管を縮めるホルモンの受容体をブロック | 副作用が少なく使いやすい。カリウム値が高くなりやすい人は注意。 |
| ③ Ca拮抗薬(カルシウム拮抗薬) | アムロジピン(ノルバスク)、ニフェジピンなど | 血管の筋肉に作用して血管を広げる | 顔のほてり・むくみが出ることがある。 |
| ④ 利尿薬 | トリクロルメチアジド、スピロノラクトン、フロセミドなど | 体の余分な水分・塩分を排出して血圧を下げる | 脱水・電解質異常に注意。トイレが近くなる。 |
| ⑤ β遮断薬 | メトプロロール(ロプレソール)、ビソプロロールなど | 心臓の働きを穏やかにして血圧を下げる | 脈が遅くなりすぎることがある。ぜんそくの人は注意。 |
| ⑥ α遮断薬 | ドキサゾシン、プラゾシンなど | 交感神経の働きを抑えて血管を拡げる | 初回はふらつきに注意。立ちくらみに気をつける。 |
| ⑦ 配合剤(2〜3種類が一錠に) | アムロジピン+バルサルタン(エックスフォージ)など | 複数の作用を組み合わせ、服薬回数を減らす | どの成分が入っているかを必ず確認。 |
2️⃣ 降圧薬を使うときの注意点
💊 ① 「飲み忘れ」を防ぐことがいちばん大事
血圧の薬は毎日決まった時間に続けることが大切です。
一度飲み忘れても急に血圧が上がるわけではありませんが、続くとコントロールが崩れやすくなります。
→ 朝食後や就寝前など、自分で習慣化しやすいタイミングを決めておくと◎。
⚠️ ② 「自己判断でやめない」
「最近血圧が下がったから」「めまいがしたから」といって自己中断するのは危険です。
薬を急にやめると血圧が急上昇(リバウンド高血圧)を起こすことがあります。
→ 中止や変更は必ず医師と相談して段階的に。
🍌 ③ サプリ・食べ物にも注意
ARBやACE阻害薬を使っている人は、**カリウムを多く含む食品(バナナ、野菜ジュースなど)**の摂りすぎに注意。
体内にカリウムが溜まりやすく、高カリウム血症になることがあります。
🚰 ④ 水分バランスを保つ
利尿薬を使っている人は脱水に注意。特に夏場はこまめな水分補給を意識しましょう。
ただし、心臓や腎臓に疾患がある方は、医師の指示に従って水分量を調整してください。
🩺 ⑤ 他の薬との飲み合わせ
風邪薬や鎮痛剤(NSAIDs)などは、降圧薬の効果を弱めることがあります。
→ 市販薬を使うときは**「血圧の薬を飲んでいます」と薬剤師に必ず伝えましょう。**
3️⃣ 薬と一緒にできる血圧コントロール習慣
🧂 減塩を意識する
日本人の平均塩分摂取量はまだ多め。
1日6g未満を目標に、しょうゆ・みそ・加工食品の量を少しずつ減らすだけでも違います。
🚶♀️ 軽い運動を習慣に
1日30分のウォーキングやストレッチで血管がしなやかになります。
無理なく続けられる範囲でOK。
🧘♀️ ストレスと上手に付き合う
ストレスは血圧を上げる大きな要因。
深呼吸・軽い瞑想・趣味の時間など、「リラックス習慣」を持つことが大切です。
☀️ まとめ
降圧薬は「一度飲み始めたら一生続ける薬」と思われがちですが、
正しく使えば合併症を防ぎ、長く健康を保つための大切なサポーターです。
「薬に頼る」のではなく、「薬と協力して健康を守る」
それが、高血圧治療の理想的な姿です。



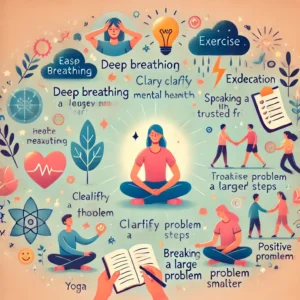



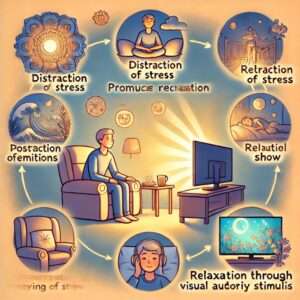



コメントを送信