🩺 糖尿病薬の種類と使い方、間違っていませんか?
🌿 はじめに
「糖尿病の薬っていろいろあってよくわからない」「どの薬が自分に合っているの?」
そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
糖尿病は血糖値(血液中のブドウ糖)をコントロールする病気です。
治療の目的は、「合併症を防ぐ」こと。そのために、お薬の役割を正しく理解することがとても大切です。
ここでは、代表的な糖尿病薬の種類と、使うときの注意点をやさしく整理します。
1️⃣ 血糖を下げる薬の主な種類と特徴
| 分類 | 主な薬剤名(例) | 作用のしくみ | 注意点 |
|---|---|---|---|
| ① インスリン分泌を促す薬(SU薬・グリニド薬) | グリメピリド(アマリール)、グリクラジド(グリミクロン)、ナテグリニドなど | すい臓に働きかけてインスリンを出させる | 低血糖に注意。食事を抜くときは服用を避ける。 |
| ② インスリン抵抗性を改善する薬(ビグアナイド薬) | メトホルミン(メトグルコなど) | 筋肉や肝臓で糖の使い方を改善 | 食後の下痢や吐き気に注意。腎機能が悪い人は使用制限あり。 |
| ③ インスリンの効きを助ける薬(チアゾリジン薬) | ピオグリタゾン(アクトス) | 細胞のインスリン感受性を高める | むくみ・体重増加に注意。心不全の方は医師と要相談。 |
| ④ 食後の血糖上昇を抑える薬(α-グルコシダーゼ阻害薬) | ボグリボース(ベイスン)、アカルボース(グルコバイ)など | 炭水化物の分解を遅らせる | 食前に服用。ガスやお腹の張りが出やすい。 |
| ⑤ 尿から糖を出す薬(SGLT2阻害薬) | ダパグリフロジン(フォシーガ)、トホグリフロジン(デベルザ)など | 腎臓で糖の再吸収を抑え、尿から糖を排出 | 脱水や尿路感染症に注意。水分補給を忘れずに。 |
| ⑥ インクレチン関連薬(DPP-4阻害薬・GLP-1作動薬) | シタグリプチン(ジャヌビア)、リラグルチド(ビクトーザ)など | インスリンの分泌を自然に促す | 効果が穏やかで使いやすい。食後に軽い胃のむかつきが出ることも。 |
2️⃣ 糖尿病薬の使い方で大切なポイント
💊 ① 「飲むタイミング」を守る
食前・食後など、薬ごとに決まった時間に飲むことが重要です。
特に食事と関係する薬(SU薬・α阻害薬)は、タイミングを間違えると低血糖や効果不足を招きます。
🍚 ② 「食事を抜くとき」は要注意
「今日は朝ごはんを抜いたけど、薬は飲んでおこう」は危険!
インスリン分泌を促す薬を飲むと、**血糖が下がりすぎてふらつく(低血糖)**ことがあります。
→ 食事を抜く日は、医師または薬剤師に相談して調整を。
🩸 ③ 「低血糖」になったらどうする?
手の震え・冷や汗・動悸・強い空腹感などは低血糖のサインです。
すぐに**ブドウ糖5〜10g(市販のタブレットやジュース100mL)**を摂取。
回復後も必ず医療機関へ報告を。
🚰 ④ 水分補給を忘れずに
SGLT2阻害薬などでは、尿から糖と一緒に水分が出ます。
特に夏場は脱水・のぼせ・ふらつきに注意が必要です。
🏥 ⑤ 他の薬との飲み合わせも確認
痛み止めや風邪薬など、市販薬にも糖尿病薬と相性の悪いものがあります。
**「薬を増やす前に薬剤師に相談」**が鉄則です。
3️⃣ お薬と上手につきあう生活習慣
薬は“対症療法”であり、治療の土台は日常生活です。
以下の3つを意識するだけでも、血糖値が安定しやすくなります。
✅ 食事: 糖質のとりすぎを避け、野菜→たんぱく質→炭水化物の順で食べる
✅ 運動: 1日30分のウォーキングでもOK(食後が効果的)
✅ 睡眠とストレス: 睡眠不足は血糖値上昇の原因。夜更かしを控える
☀️ まとめ
糖尿病の薬は「数が多くて難しそう」と感じますが、
それぞれが違う角度から血糖を下げるチームプレーヤーです。
大切なのは、
- 自分の薬の役割を知る
- 正しいタイミングで服用する
- 体調変化を感じたら医師や薬剤師に相談する
「薬に振り回されず、薬を味方にする」——それが糖尿病治療の第一歩です。



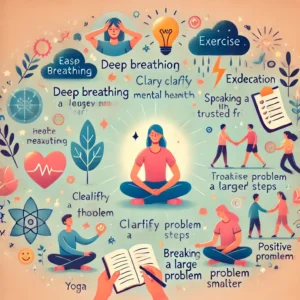



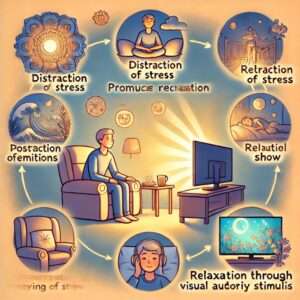



コメントを送信